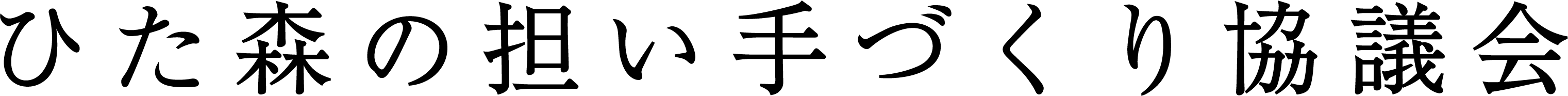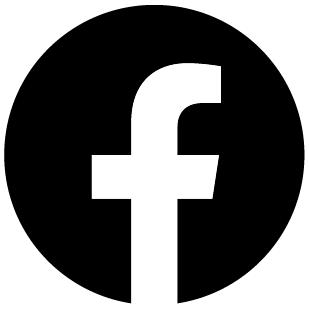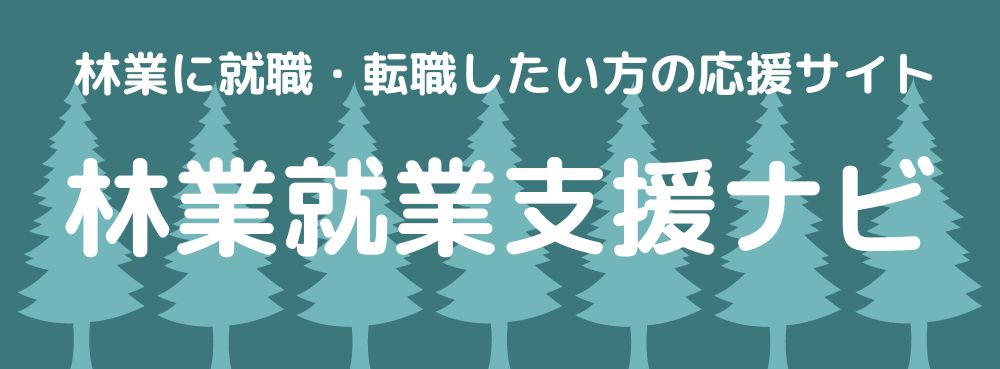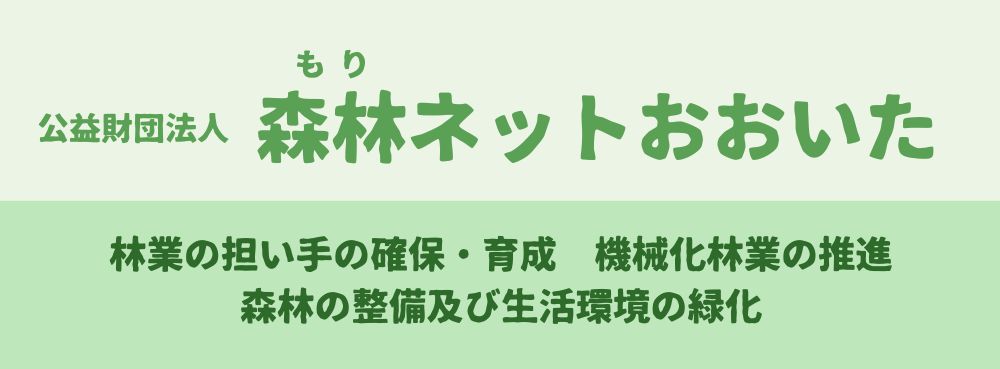11月9日、温暖化の影響か、秋とは思えない暖かさのなか、ひた森勉強会2024の第2回目研修を開催しました。
今回の集合場所は前津江地区。遠くは宮崎から参加する方も!

参加者が揃ったところで、ひた森の担い手づくり協議会・諌本会長と企画部会長のナンブ木材・武内さんよりご挨拶。第1回目の座学とは異なり、今回は実践研修。森仕事を肌で感じられる一日になりそうです。
森の中で学ぶ「地拵え」
澄んだ青空の下、鳥のさえずり、川のせせらぎ、風の音に包まれながら、いざ現場へ。

本日のテーマは、「地拵え」「植え付け」「鹿ネット」「安全対策」。講師を務めてくださるのは、マルマタ林業の合原万貴さん、高山さん、日田市森林組合の黒木さん、関谷修さん、関谷直さんの5名です。
まずは「地拵え」から。
「地拵え(じごしらえ)」とは、伐採された山に苗木を植える前の準備作業。林業初心者の広報チームは、昨年の研修までこの言葉すら知りませんでした。山に苗木を植えるには、ただ掘って埋めるだけではダメ。枝や葉を整理し、土壌を整えることが必要なのです。
まずは、合原さんが地拵えの種類を解説。
・棚を組む地拵え(一般的)
・枝をバラバラにしてそのまま植え付ける地拵え
・火入れで燃やす地拵え
・谷に枝を落とす地拵え
という、地拵えのうち今回は「棚を組む地拵え」を行います。
いざ、地拵え開始!
3班に分かれ、作業スタート!「鎌を持ったまま転ぶと大怪我に! 気をつけて作業しましょう!」「よろしくお願いしますっ!」と元気よく掛け声をかけ、作業開始。
地面に落ちた枝を集め、斜面に木の枝を刺し、枝葉を引っ掛けていく作業は、まるでビーバーの家づくりのよう。

ここで黒木さんが問いかけます。「1ヘクタールは何平米でしょう?」
……数字に弱い広報チームはすぐに答えられませんでしたが、正解は 10,000平米(1万平米)。
山主さんの希望で、1ヘクタールあたり2,000本の苗木を植える計画なら、1本あたり5平米のスペースが必要。計算すると、2.2メートル × 2.2メートルの間隔で植えることになります。
ちなみに、2,500本の場合は2メートル間隔、3,000本の場合は1.8メートル間隔。この計算に基づき、実際に地拵えを進るのだそう。

作業は安全第一!安全対策も忘れずに
鎌の持ち方や ヘルメットの着用、上下作業の禁止(落石防止のため)、 チェーンソーや下刈り機の免許取得推奨、雨の日は特に注意!など、安全対策についてもレクチャーいただきました。
そしてお昼休憩は各自お弁当タイム。「日田弁わからないアルアル話」など参加者同士で談笑しながら盛り上がる場面も。作業をしながら自己紹介をしたり、道具の扱いについての知識を深めたりと、和やかな時間が流れます。
そして、午後からは植え付け作業!
苗木は「コンテナ苗」。専用の道具を使い、根腐れしないように植え付けます。

ここで講師から豆知識。ヒノキは日の当たる方向に向かって育つ性質があるため、「表」と「裏」があるとのこと。間違った向きで植えると、ねじれて成長してしまうのだとか!ベテランでも「スギの表裏はよく分からん」とのこと(笑)。
方角が分からないときは「班長に聞くのが吉」だそうです。
最後は「鹿ネット」設置!
最後は、植えた苗木を守るため、鹿シェルターと鹿ネットを設置しました。
くるくるっと巻いて固定するだけに見えるものの、「見ていると簡単そうだけど、やると意外と難しい!」という参加者。何事も、経験とコツが大事ですね。

研修の最後に、関谷修さんが「前の作業が雑だと、後の作業が大変になる」という、森仕事の基本を教えてくれました。
道具を大切に扱い、安全に配慮しながら作業を進めることが、結果的に効率的な仕事につながるということですね。
森仕事のリアルを体感した一日。自然の中で学ぶことの多さを実感しました。作業は大変だけど、充実感もひとしおでした。
今回の研修も、西日本新聞社の床波さんが記事にしてくださいました。こちら「林業担い手育成「ひた森勉強会」参加してみた 「地ごしらえ」に悪戦苦闘」からご覧いただけます。